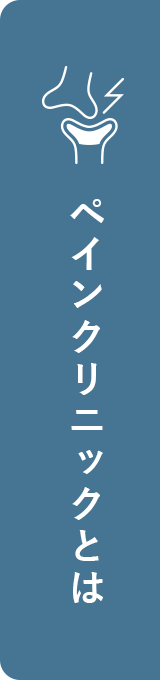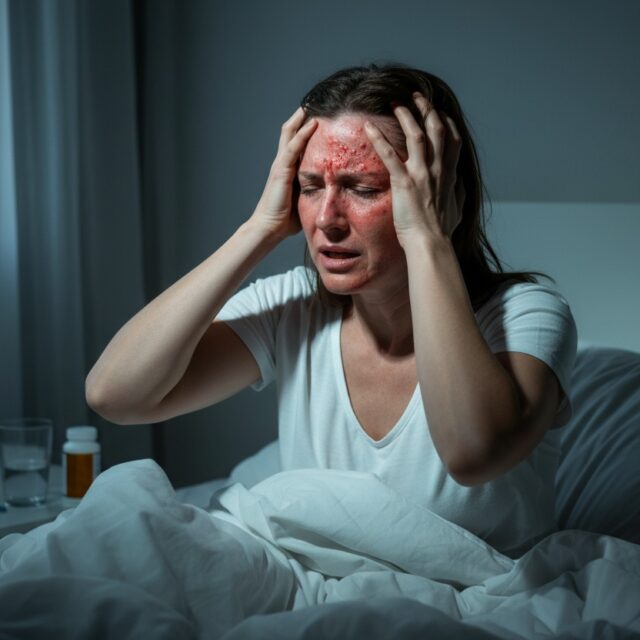目次
「少し体を動かすと、なんとなく痛みがラクになる気がする」
そんな経験をされたことはありませんか?
実はこの“運動で痛みがやわらぐ”という現象には、
脳や神経が本来持っている「痛みをコントロールするしくみ」が関係しています。
このしくみは、医学的にEIH(Exercise-Induced Hypoalgesia)=運動による疼痛緩和と呼ばれ、
慢性の痛み治療にも応用されつつあります。
今回は、EIHのしくみや、治療としてどう活かせるのかを、わかりやすくご紹介します。
「ランナーズハイ」も同じしくみ?
長距離を走ったあとに気分がスッキリしたり、痛みがやわらぐことがあります。
これは「ランナーズハイ」と呼ばれ、脳内で“痛みを抑える物質”が自然に分泌されている状態です。
このしくみと同じように、適度な運動が慢性の痛みにも良い影響を与えることが、近年の研究で明らかになっています。
脳と脊髄にある「痛みを抑える回路」が働く
運動によって体にかかる刺激は、脳幹や中脳に伝わります。
その中でも特に重要なのが「下行性疼痛抑制系」という神経回路です。
●中脳のPAG(中枢水道周囲灰白質)が反応し
●延髄のRVM(延髄吻側腹内側部)を経由して
●脊髄に「痛みを抑えろ」という信号が送られます
この信号によって、痛みの情報が脳に届く前に“ブレーキ”がかかるのです。
運動によって出る「天然の痛み止め」
運動中、脳や神経では以下のような鎮痛物質が分泌されます:
-
🧠 エンドルフィン:幸福感と鎮痛作用をもたらす「脳内モルヒネ」
-
🔒 エンケファリン:脊髄で痛み信号をブロック
-
😊 セロトニン:気分を安定させ、痛みを感じにくくする
-
⚡ ノルアドレナリン:痛みの伝達をしずめる作用
-
💡 ドーパミン:痛みの“つらさ”を軽減する働き
-
🌿 内因性カンナビノイド:炎症や神経の過敏を抑えるとされる注目物質
これらはすべて、私たちの体が本来持っている“天然の痛み止め”です。
運動は、それらを自然に引き出すスイッチのような役割を果たしているのです。
ガイドラインでも推奨されている「運動による疼痛緩和」
日本ペインクリニック学会の『慢性疼痛診療ガイドライン(2021年)』では、
慢性疼痛に対する運動療法は「推奨度A」「エビデンスレベル高」と明記されています。
とくに、慢性的な腰痛や神経過敏をともなう痛みに対しては、
脳や神経を“痛みを抑える方向へ”再調整する効果が期待されています。
院長の実感:運動は「痛みを改善するきっかけ」になることが多いです
私自身、神経ブロックや薬だけでは十分に痛みが改善しないケースを多く経験しています。
そんな方でも、痛みが少しやわらいだタイミングで軽い運動を始めると、
「自分で痛みを意識しないようになった」と感じられることがよくあります。
とくに慢性の痛みでは、「動けた」という成功体験が“痛みの悪循環”から抜け出すきっかけになることを、
日々の臨床で実感します。もちろん、無理をする必要はありません。
状態に応じたペースと方法を一緒に考えていきますので、どうぞご安心ください。
まとめ|運動は“痛みに強くなる脳”をつくるきっかけに
「運動したら痛みが軽くなった気がする」
それは、体が本来もつ“鎮痛力”がうまく働いている証拠かもしれません。
なかお三国ペインクリニックでは、
神経ブロックとリハビリを組み合わせ、
「動ける体」「痛みに強くなる脳」を一緒につくる治療を行っています。
長引く痛みにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
参考文献(抜粋)
●日本ペインクリニック学会『慢性疼痛診療ガイドライン 2021年改訂版』
●Polaski AM, et al. Exercise-induced hypoalgesia: A meta-analysis of exercise dosing for the treatment of chronic pain. PLOS ONE. 2019;14(1):e0210418.
●Lima LV, et al. Exercise-Induced Hypoalgesia: A Meta-analysis. J Pain. 2017;18(8):545–552.
※本記事は、上記の研究をもとに医師が監修・執筆した内容です。